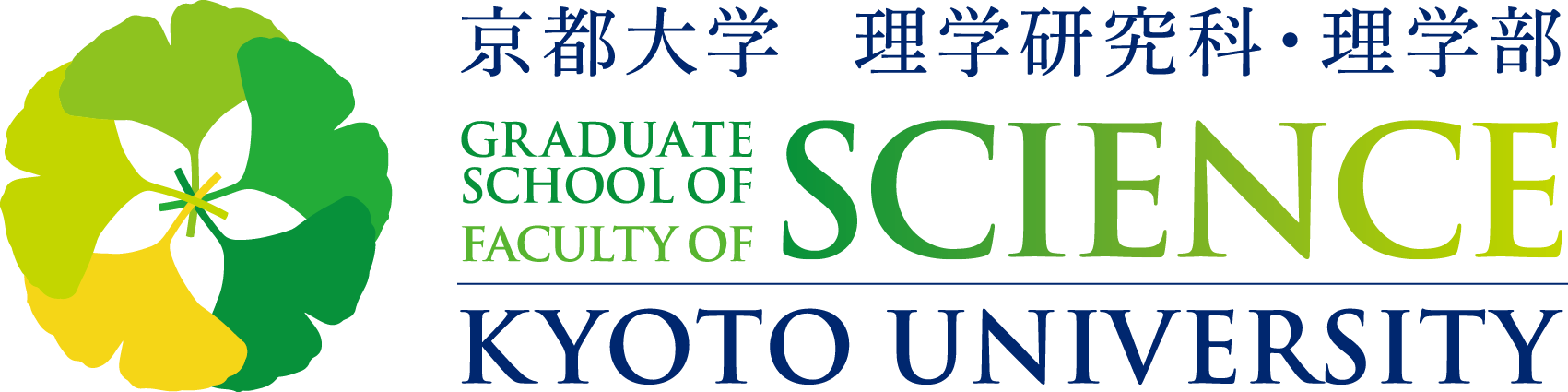京都大学基礎物理学研究所・特任教授 九後 太一
益川敏英先生が2021年7月23日に亡くなられた。享年81歳だった。
益川先生は、私が京大理学部の大学院に入学して指導を受けて以来50年の間、先生が東京大学助教授だった4年間を除けば、ずっと京都(京都大学および京都産業大学)にいらっしゃって、私はいつも近くにいる事ができた。学問ばかりでなくあらゆる事を教えていただいた文字通りの師であるが、師の教えに従い益川先生と呼ぶのはここまでにして、ここ以降益川さんと呼ばせていただく。益川さんとの多分に個人的な思い出が多くなるが、益川さんの人となりについて書き、故人を偲びたい。
名古屋大学から京都大学助手へ
湯川秀樹博士が定年を迎え京都大学基礎物理学研究所を退官されたのが1970年3月末であるが、益川さんはそれと入れ替わりに、5月に旧湯川研である京都大学理学部物理学第二教室の素粒子論研究室の助手に着任された。
今から思えば、当時、世界の素粒子論は大きな転回点にあった。1960年代は、次々と出てくる膨大な実験データを前にして、理論は何も明確なことが言えず、進むべき方向性を暗中模索する状態であった。特に、素粒子の世界を語る基本的な言語とも言える「場の理論」自体が、全く信用を失っていた。場の理論は、そもそも素粒子論が1930年代前半にFermiの弱い相互作用の理論や湯川の強い相互作用の理論(=中間子論)によって始まった時から使われ、その無限大が生じるという困難も朝永振一郎、Schwinger、Feynman、Dysonらの量子電気力学に対するくり込み理論で克服され、1950年頃までには、摂動論としてはほぼ完成された理論であった。にもかかわらず、それが膨大な実験データを前に全く無力で信用を失っていたのには、二つの理由があった。一つは、原子核を構成する陽子や中性子、そして湯川の予言したπ中間子などを初めとした、ハドロンと呼ばれる非常に多くの素粒子たちが続々と発見されていたのであるが、それらは本当に強い相互作用をしており、そのため量子電気力学で成功した摂動論が計算法として無力であったことである。もう一つは、それらのハドロンが、実は「素」粒子ではなく、もう一つ下の階層の、今日クォークと呼ばれる基本構成子が存在する、という認識になかなか到達しなかった、せいである。
これらは、素粒子論という学問が、湯川博士が「未知の世界を探究する人々は、地図をもたない旅人である」と記したように、実に先が見えない研究分野であることを痛感させる。
ともあれ、益川さんは、坂田模型以来の素粒子複合模型の研究に伝統のある名古屋から京都に来られ、彼自身は南部陽一郎博士の提唱されたカイラル対称性の自発的破れの理論など、場の理論にも造詣の深い気鋭の若手研究者であった。
益川さん着任の70年4月に新M1(修士一年生)として入学してきた学生達(植松恒夫、東島清、山脇幸一)は、大学紛争のさなかに大学院入試があり、妨害を避けるため大原のお寺で受験して通ってきた猛者達の大変元気な学年で、益川さんにカリキュラム外の講義やセミナーを頼んでやってもらっていた。私は次の年の71年4月からM1として入ったのだが、この恩恵に浴して益川さんからカイラル対称性の破れの理論などの場の理論の講義を聴く事ができた。また、1967年にWeinbergが提唱していた、電磁相互作用と弱い相互作用を統一する、電弱統一ゲージ理論を、益川さんは我が研究室のコロキウムで初めて紹介した。その理論は、量子電気力学より高次の局所対称性を持つ「非可換ゲージ理論」に対して南部博士の自発的対称性の破れを適用して、力を媒介するゲージ粒子とともに電子などの物質粒子にも質量を持たせる理論である。提唱者のWeinbergは、そういう非可換ゲージ理論も、量子電気力学と同じく、無限大の困難がないくり込み可能な理論であろう、と予想していたが、実際71年には弱冠25歳の't Hooft (トホーフト)がそのくり込み可能性を証明する論文を発表していた。私がその難解な論文を理解したいというので、益川さんは私の修士論文に向けた個人指導のような形で毎週彼の部屋で一緒にその論文を「輪講」してくださった。それは私がM2になったばかりの72年4月頃だった。
小林・益川理論の誕生
ちょうどその4月に、名古屋大で学位を取って大学院を修了したばかりの小林誠さんが、助手として素粒子論研究室に赴任された。2年ぶりに再会した益川、小林のご両人は、せっかくまた同じ場所で働くことになったので、何か一緒に研究しようということで、「くりこみ可能な電弱統一ゲージ理論にCP対称性の破れはどのように入れられるのか?」という共同研究を始めたのである。CP対称性とは、素粒子の粒子と反粒子の間の対称性のことで、その破れは、この宇宙に粒子が反粒子よりも圧倒的に多く存在するのは何故か?という問いに答えるために必要なのである。そのわずかな破れが実際1964年に実験的に発見され、名古屋の博士課程に在籍中の益川さんが、研究室の速報でその論文を紹介した。が、その問題は当時としては理論的に全く説明するすべのない問題で、益川さんは「この問題は時期が来るまで暖めておこう」と思ったとのことである。
72年4月の小林さんとの再会の時に、そのCP対称性の破れの問題にアタックすべき時期が来た、と思ったわけである。その共同研究は5月の連休明けくらいから本格化する。益川さんは、当然私への研究指導と小林さんとの議論は時間を分けていたが、時々、私への指導が予定の時間を超えることがあり、次に予定していた小林さんがやってきて私の目の前でその議論を始める、ということが何度かあった。しかし目の前で進行していた研究ではあったが、残念ながら私には未だその内容は良く理解できず、彼らの議論に参加することができなかった。
夏休み明けの9月に、素粒子論研究室でコロキウム(毎週一回の、研究室内外の人が自身の新しい研究を発表するセミナー)が行われた。まだ出来たばかりの論文の京大物理教室の孔版刷りのプレプリントを片手に持って、それを参照しながら、小林誠さんが、できたての小林・益川の仕事を研究室で紹介した。
私は、このコロキウムで話を聴いた時、「くりこみ可能なゲージ理論という枠組みの中で、CP対称性の破れという一つの実験事実から、クォークという自然界の基本構成子の存在に対して制限が付けられる」という点において「方法論的には大変おもしろい」とは思った。しかし同時に、「6種類以上クォークが存在せねばならない、という予言はまず間違っているだろう。小林・益川自身がその論文で指摘している他の可能性や、もっと別の模型の可能性が実現しているに違いない」と思った。その頃は、実験的には未だ、アップ、ダウン、ストレンジの3種類のクォークしか知られていなかったし、また自然界の基本構成子としては3種類もあれば十分多いという意識が強かったせいである。
それにしても、小林・益川のこの仕事は、小林さんの京都への引っ越しなども落ち着いた5月初めから本格的に始まり、6月の末にはもう本質的なところは出来ていた。ただ論文を書き上げるのに2ヶ月を要した。先ず、益川さんが日本語のドラフトを作成するのに1ヶ月、その後小林さんが英語にして最終稿を完成するのにさらに1ヶ月かかった、とのことである。湯川さんの創刊した欧文学術誌「プログレス」に投稿されたその論文の受理日付は72年9月1日である。議論に非常に集中した二人だったとは思うが、2ヶ月余りであのような仕事がなされたことに驚嘆する。素粒子論の将来の方向に対する正しい見通しと、適切な問題設定が如何に大事であるかということを痛感させられる。
当時、ワインバーグ・サラム模型(と呼ばれていた電弱統一ゲージ理論)が予言する中性カレントが実験でなかなか見つからないため、中性カレントの存在しない色んな亜流モデルも数多く提案されていた。にもかかわらず、あの論文ではまっすぐに、歴史的に最終的に残ることになるワインバーグ・サラム模型でだけ、CP対称性の破れを入れる可能性を論じているのである。これなども、明らかに彼らの見通しの良さを物語るものである。
この小林・益川の仕事は、「自然界において三世代6種類以上のクォークの存在を予言する(CP)対称性の破れの起源を発見した」ことに対して、2008年のノーベル物理学賞を授与されることになる。実に論文発表から35年後であるが、それは、小林・益川理論が予言する、三世代6種類のクォークが全て発見され、さらにそのクォーク間の混合がCP対称性の破れの機構としても正しいことが確認されるためには、いくつもの世界の大規模な実験が必要だったためである。益川さんは、日本語で行ったノーベル賞受賞講演を
「しかしながら、この理論が本当に確かめられるのは、30 年余りという長い年月と多くの実験家たちの莫大な努力とが必要でした。私はここに、この人類の壮大なプロジェクトを支えた世界中の人々に感謝したいと思います。」
という、簡潔ながら感銘深い感謝の言葉で結んでいる。
助手時代の益川さん
益川さんの京都大学での助手時代は、76年3月に東京大学原子核研究所に助教授として転出するまで、6年間である。
その間彼は、素粒子論研究室で毎週、研究室メンバーが集まって「場の理論」の新しい論文を読んでゆくゼミ(勉強会)を主宰していた。多くの年は、その年に修士論文を書く大学院生を中心にしてゼミを組むので、その学生の名前を冠して「井上ゼミ」などと呼んでいた。隣の基礎物理学研究所の助手だった福田礼次郎さんらも参加し、かなり多くのメンバーを擁したゼミだった。こういう形で、若い人々をリードし、京都大学素粒子論研究室に新しい場の理論の伝統を根付かせた。
先に、小林・益川の見通しの良さと書いたが、このゼミなどを中心として益川さんが我々若い院生たちに語っていたビジョンはすごかった。あの混沌としていた60年代の素粒子論が、弱・電磁相互作用ばかりか強い相互作用までを含めた全ての相互作用の理論が局所ゲージ対称性を起源とするゲージ理論に収束してゆく大きなパラダイム転換の流れを見通していたのである。
益川さんは、このような直接的な研究上の指導以外に、色んな折りに、若手と話をするのが好きで、それを通じて結果として若い人を鼓舞・激励していた。印象に残っている話を一つだけあげておけば、益川さんは自身を「益川先生」と呼ばせない、ということである。私などは実際に研究上の指導も受けているので益川先生とつい出てしまう。しかし、大学院に入った学生は皆研究室の教員を「先生」でなく「さん」付けで呼べ、というのである。そこでまた一家言がある。院生が教員をさん付けで呼ぶことによって、教員も院生も「研究者として対等」である、ということを自他ともに意識させることが重要である。特に、院生にとっては、明らかに経験も知識も多い教員と対等であると宣言することによって、実質でも対等になろうと背伸びする効果がある。また教員の方も、名前でなく実質によって自然と尊敬されるべきものである、というようなことを、いつも若手に言っている。しかし、このように文字にすると、あの懐かしい「益川節」がうまく再現できていない気がする。
性格は、あまのじゃく。常識的な考えや期待には、その通りに答えることは大嫌いで、必ず逆のことを答える。自分で『いちゃもんの益川』と称しておられたが、それもそのことと同根のことであり、色んなことに益川流の一家言がある。またそれをまわりの若い人によく「垂れる」。気は強い、と思う。少なくとも弱みを見せるのは嫌い。(しかし、私はかつて益川さんから「講演などうまくできるかどうか不安になった場合は『大丈夫、必ずできる』と自身に言い聞かせる」のだと聞いたことがある。益川さんでもそういうことがあるのかと感銘を受け、以来この言葉は私の不安解消の言葉になっている。)
これら全ての特質は、良く言えば「反骨」である。実際、色んな会議でもその場の雰囲気でなかなか正論が言えない場面が多いものであるが、益川さんはそういう場合でも必ず筋を通した意見を述べる。それをどんな「立派な」会議でも臆さず実行されていたようである。

脚を抱えているのは筆者(1976年3月、東大へ転出の際
ふたたび京都に
益川さんは、東大原子核研究所には結局4年おられたが、1980年に基礎物理学研究所教授として京都に戻って来られ、90年には私が助教授でいた理学部物理学教室に移ってきていただいた。益川さんが最も幸せで、私にとってもありがたかったのは、この物理教室素粒子論研究室で、教授と助教授、教授と教授の関係でご一緒させていただいた6年あまりの期間である。その頃には益川さんは、自分の研究というのは余り表立ってはされてなかったが、研究室の学生やスタッフとの研究談義や交流、学部生の教育、教室の運営、など、あらゆることを楽しんでされていた。私は、益川さんの陰に隠れて気楽に研究をさせて頂いただけでなく、研究室の主宰者や教室のリーダーになった場合に行うべき色んなことを教わった。益川さんにとってその頃が最も幸せだっただろうと想像するのは、やはり、基研のような研究所ではなく物理教室だと、直接に接する大学院の学生が大勢いる、という点である。学部の授業を通して学部学生と交流することも楽しまれたが、大学院の学生に囲まれて彼らと最新の研究のこと、昔の坂田先生や坂田研究室のこと、益川さんが助手時代の素粒子論研究室のこと、若手が持つべき研究者としての心意気、など、自在に語られるのが何より好きだったのである。
素粒子論研究室で毎年正月に行う「新春放談会」では、益川家から寿司桶一杯の寿司飯と、寿司ネタの新鮮な造り、手巻き用のり、が届けられ、他のスタッフが持ち寄った色んな料理と共に、研究室のメンバーがそれらを頂きながら、めいめい、その年の抱負や夢やホラを語る。夏には2泊3日ほどの研究室合宿に出かける。そういう折にはとりわけ、益川節を聞かせていただけるのだが、大変楽しそうであった。
しかしこういう機会も、95年には京大の評議員、そして学生部長、留学生センター長,体育指導センター長を併任され、大学の仕事が忙しくなってからは残念ながらめっきり減ってしまった。実際、学生部長としては、学生と気さくに話をされ、多くの時間を割いて誠実に対応されたので、学生からの信頼も厚かったが、大変忙しくされていた。
97年には理学部からふたたび基礎物理学研究所に移り、 2003年3月までの3期6年間、基研所長を務められ、その全国共同利用研究所としての運営と発展に尽力された。その間も、学内では評議員、学外でも文部省所轄ならびに国立大学付置研究所所長会議の会長(任期1 年)、さらには、第17期日本学術会議会員(第4部、任期3年)を務め、国立大学法人化の荒波の下で、基礎物理学研究所や広く全国共同利用研究所のあるべき姿について発言され、学内的にも、全国的にも大きな役割を果たされた。
ノーベル賞
2003年に京都大学を定年退職されて後は、京都産業大学に移られ、久しぶりに若い学部学生達に物理を教えることを楽しまれた。そこで2008年になってようやく上述の小林・益川の業績でノーベル賞を受賞される。京都産業大学はこれを記念して、基礎物理学のポスドク研究者を育成・支援する「益川塾」を立ち上げるが、益川さんは2020年の退職まで塾頭としてその任に当たられた。(私はここでも京大の定年後、益川塾副塾頭として呼んで頂き、ご一緒させていただいた。)この機に、京都大学は、北部総合教育研究棟 (Maskawa Building for Education and Research) を建て、その一階には益川ホールおよび小林・益川記念室を作った。母校の名古屋大学は学内に素粒子宇宙起源研究機構(Kobayashi-Maskawa Institute, KMI)を立ち上げ、益川さんはその機構長を兼任することになった。
2008年のノーベル物理学賞は、10月7日に受賞者の発表があったが、先述のように三世代6種以上のクォークの存在を予言してCP対称性の破れの機構を発見した小林・益川の両氏に対して、と同時に、「素粒子物理学における対称性の自発的破れの機構」を発見した南部陽一郎博士との共同受賞であった。日本人三人の独占受賞ということでも話題になった。それ以上に、受賞の報を受けた後の京都産業大学で行われた記者会見で益川さんは(ノーベル賞の受賞は)「大してうれしくない」などとあまのじゃくの発言を続けていたのだが、若いときから尊敬してきた南部陽一郎先生との共同受賞であったことに話が及んだとき彼が感極まって涙したことが多くの人々の胸を打った。この時の記者会見は、益川さんの飾らない率直な物言いやお茶目で気さくな人柄が一般の人から好感されるきっかけになった。ノーベル賞受賞後は、本当に全国のいろんな所に講演に行かれ、若い人たちにも一般の人々にも、基礎科学の面白さや重要性を広くそして柔らかく伝えられる伝道師の役割を果たされることになった。この京大理学部でも、毎年、新入生達に対して講演会を行っていただいた。

(ストックホルム大学、2008年12月8日、photo by Kenji Matsui )
益川さんは、卓越した物理学者である一方、平和運動や科学研究のあり方などの社会問題にも忖度無く発言する気骨の研究者だった。研究室の院生や若手研究者に対してそういう問題を表立って話されることはあまりなかったが、幼少の頃に経験した戦争体験から平和への思いは特に強く、社会に対してもずっと発言を続けて来られた。先日は、学術会議会員任命拒否問題に関して病を押して声明を発表された。しばらくお会いしていない中でその報道に接し、益川さんの思いに心を致すとき、万感胸に迫るものがあった。
私が大学院に入学して以来この50年の間、益川さんはずっと近くにいらっしゃった。私はいつも益川さんの背中を追いかけてきた気がします。もちろん益川さんは大きすぎて遂に追いつけなかったのですが。その益川さんがもういらっしゃらないのを大変寂しく思います。
益川さんの生き方に深く敬意を表しますとともに、我々後進を導き日本の科学研究に多大な貢献をされたことに深く感謝申し上げ、ご冥福をお祈りいたします。

(この会議の結びの言葉で南部陽一郎博士が小林・益川理論にお墨付きを与えた)