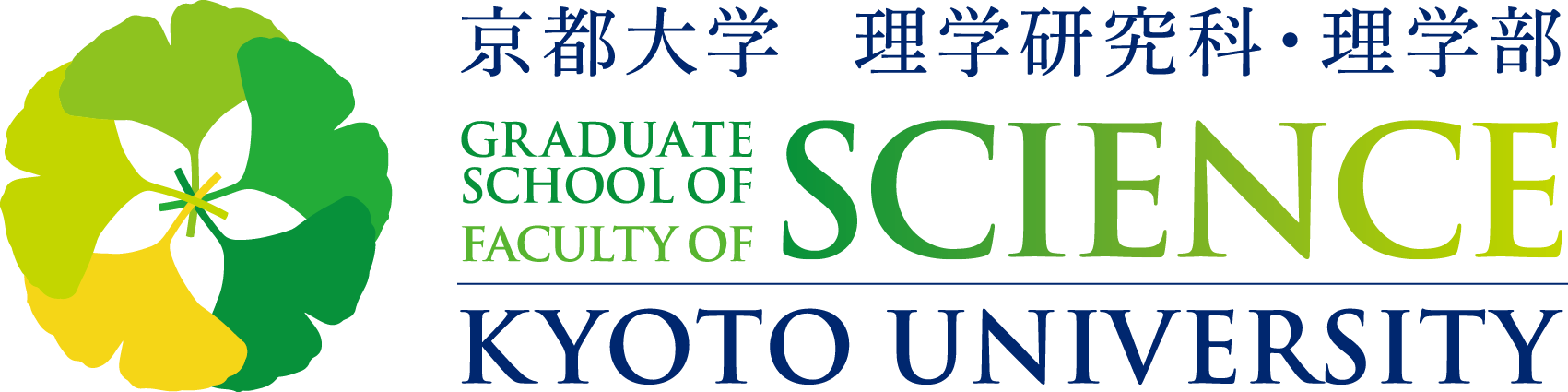京都大学 前総長 山極 壽一

私は玉城記念講演会が始まった1年後の1970年に京大に入学しました。1970年と言う年は、「人類の進歩と調和」を掲げた万博と、日本は戦後、日本を失ったんではないか、という問いを突き付けて三島が割腹自殺をするという、対照的なメッセージが発せられた年でした。われわれは高校時代からこの二つのギャップに悩みつつ、大学という学問の道に歩み始めました。
今西さんは、アルピニストで学術調査探検活動を展開して学問の裾野を広げるとともに、アフリカ類人猿調査を牽引して京大の霊長類研究の基礎を固めました。霊長類学といわれる学問が生まれ1950年代には、伊谷さんが大分県の高崎山でサルにもきちんとした社会構造があることを証明しました。また今西さんの一番弟子の梅棹忠夫さんは独自の文明論を展開して今西人類学に奥行をもたらしました。今西さんが始められた人類学教室は、自然人類学と人類進化論の2つの系譜に分かれ、今日に至っています。
それで大学院入学時、伊谷さんに社会の変異の研究をしたいと希望を出しましたが、一人で何地域ものサルの群れを研究するのは無理と言われ、その代わりサルの外部形態の変異を調べることになりました。教授の池田次郎さんに師事し、骨についての非計測的特徴を多変量解析で比較する方法を用い、9地域、合計2千頭近いサルの外部形態の比較をし、地理的な変異に加え、長い間隔離されて交流が途絶えている地域では独自の形態的な特徴を備えていることを明らかにしました。それが私の最初の論文です。
ただ、伊谷さんとその後の研究者が行っていたニホンザルの社会学的研究はほとんど餌付け群での研究でした。1970年代になると、餌付けをすることの問題点が指摘され、自然状態での研究が始まりました。最初の頃の研究フィールドは視界が確保しやすい積雪地に限られていましたが、私たちはサルの群れが多く、照葉樹林で林床植生が発達していないため視界がよい屋久島での研究に着手しました。そして、自然群の分裂を初めて観察しました。
後に、冷温帯林の金華山島で伊沢紘生さんたちが行ってきた研究との比較検討を多くの研究者とともに行い、ニホンザルの基本的な社会構造は変わらないものの、環境によって群れの分裂の仕方やオスの群れへの入り方が違うという変異があることが明らかになりました。私が最初に興味をもった今西・伊谷論争から実に24年間もかかりましたが、やっと納得のいく解釈をすることができたと思っています。
その結果ゴリラとチンパンジーが全く対照的な社会構造をしており、両種に共通していることは、メスだけが集団間を移動できるということが分かりました。また、ゴリラの社会は、オスが人間の家族を彷彿させるような父性行動を示し、チンパンジーは道具を使ったり、肉食をしたりといった人間社会の起源を思わせるような知的な行動がよく見られるということも分かってきました。
そしてオスがまず集団を離れて、1頭のメスを娶り、そのメスを増やしていき、子孫を増やし、その集団が息子に継承されるか、バラバラになるかどちらかへ変化することを明らかにしました。これが私の学位論文になりました。この研究でゴリラでは内部要因によって社会が変異をするということを確信しました。
ゴリラ研究が楽しく思えていた1985年、ダイアン・フォッシーが殺害されるというショッキングな事件が起こりました。私はヴィルンガから、低地まで広がるカフジ・ビエガへと調査地を移し、そこで日本やコンゴの研究者とチームを組んでゴリラの社会の外的、内的要因による変動について調べました。その結果、標高が高くフルーツが少ないヴィルンガと低地でフルーツが多いカフジで集団の大きさと構成が異なることが分かりました。これを論文に出したのは2009年です。ここまで来て環境という外部要因による採食戦略、群れ内外の社会関係による内部要因が社会構造の変異をもたらしていることが分かってきたように感じました。
そして共食や共同保育によって育てられた高い共感力で、人間は一生涯自分が出てきた共同体にアイデンティティを持ち続け、そして集団というものを強く意識することになりました。そこに7万年ぐらい前に言葉が登場して認知革命が起こり、共感と対話という能力が結びついて想像力と創造力が拡大することになります。
今日地球はいくつかの指標で限界値に達し、情報革命による意識と知能の分離が起こり、遺伝子編集、生物工学による人間の改造の可能性が進む中、新たな人間の社会性を再構築しなくてはなりません。その時に故きを温ね、人間に近い隣人の行動様式や社会を探る霊長類学、人類学がお役に立てるだろうと思っています。
京大理学部発の人類学
今西錦司さんは内蒙古出征時の研究がきっかけでウマの社会の研究をしようと宮崎県の都井岬に出かけました。そのとき川村俊蔵さん、伊谷純一郎さんらとともにニホンザルの群れを見て感激し、サルの社会の研究をすることになったのです。この日1948年12月3日が、日本の霊長類学誕生の日になります。今西さんは、アルピニストで学術調査探検活動を展開して学問の裾野を広げるとともに、アフリカ類人猿調査を牽引して京大の霊長類研究の基礎を固めました。霊長類学といわれる学問が生まれ1950年代には、伊谷さんが大分県の高崎山でサルにもきちんとした社会構造があることを証明しました。また今西さんの一番弟子の梅棹忠夫さんは独自の文明論を展開して今西人類学に奥行をもたらしました。今西さんが始められた人類学教室は、自然人類学と人類進化論の2つの系譜に分かれ、今日に至っています。
種の社会構造への興味~今西・伊谷論争から
1974年、私は、一つの種には一つの社会構造しかないと考える伊谷さんと、種の社会構造というのは安定したものではないという今西さんの師弟論争を目の当たりにしました。この論争で、社会はどのように変動するのか、そしてその要因は何か、という疑問が浮かび上がり、それに大変興味を持ちました。それで大学院入学時、伊谷さんに社会の変異の研究をしたいと希望を出しましたが、一人で何地域ものサルの群れを研究するのは無理と言われ、その代わりサルの外部形態の変異を調べることになりました。教授の池田次郎さんに師事し、骨についての非計測的特徴を多変量解析で比較する方法を用い、9地域、合計2千頭近いサルの外部形態の比較をし、地理的な変異に加え、長い間隔離されて交流が途絶えている地域では独自の形態的な特徴を備えていることを明らかにしました。それが私の最初の論文です。
ただ、伊谷さんとその後の研究者が行っていたニホンザルの社会学的研究はほとんど餌付け群での研究でした。1970年代になると、餌付けをすることの問題点が指摘され、自然状態での研究が始まりました。最初の頃の研究フィールドは視界が確保しやすい積雪地に限られていましたが、私たちはサルの群れが多く、照葉樹林で林床植生が発達していないため視界がよい屋久島での研究に着手しました。そして、自然群の分裂を初めて観察しました。
後に、冷温帯林の金華山島で伊沢紘生さんたちが行ってきた研究との比較検討を多くの研究者とともに行い、ニホンザルの基本的な社会構造は変わらないものの、環境によって群れの分裂の仕方やオスの群れへの入り方が違うという変異があることが明らかになりました。私が最初に興味をもった今西・伊谷論争から実に24年間もかかりましたが、やっと納得のいく解釈をすることができたと思っています。
サルから類人猿へ~人間社会の起源を求めて
今西さんは社会が人間と動物で連続したものであり、サル、類人猿、人間と連続しているに違いないと考えていました。最初の類人猿調査を1958年にゴリラを対象に始めたのですが、ゴリラの生息域が当時アフリカの独立紛争にほとんど巻き込まれてしまったため調査ができなくなり、巻き込まれなかったタンザニアの調査地でチンパンジーの調査を行うことになりました。その結果ゴリラとチンパンジーが全く対照的な社会構造をしており、両種に共通していることは、メスだけが集団間を移動できるということが分かりました。また、ゴリラの社会は、オスが人間の家族を彷彿させるような父性行動を示し、チンパンジーは道具を使ったり、肉食をしたりといった人間社会の起源を思わせるような知的な行動がよく見られるということも分かってきました。
ゴリラの社会構造の変異
1978年に伊谷さんから、お前、体が大きそうだからゴリラをやってみないか、と言われて、コンゴ盆地の東端にあるカフジ山というゴリラ生息域に調査に出かけました。野生のゴリラは手ごわく、9か月の苦戦の後、伊谷さんが話をつけてくれて、ヴィルンガ火山群にあるダイアン・フォッシーの調査地へ移りました。そこで2年間調査をさせてもらいました。そしてオスがまず集団を離れて、1頭のメスを娶り、そのメスを増やしていき、子孫を増やし、その集団が息子に継承されるか、バラバラになるかどちらかへ変化することを明らかにしました。これが私の学位論文になりました。この研究でゴリラでは内部要因によって社会が変異をするということを確信しました。
ゴリラ研究が楽しく思えていた1985年、ダイアン・フォッシーが殺害されるというショッキングな事件が起こりました。私はヴィルンガから、低地まで広がるカフジ・ビエガへと調査地を移し、そこで日本やコンゴの研究者とチームを組んでゴリラの社会の外的、内的要因による変動について調べました。その結果、標高が高くフルーツが少ないヴィルンガと低地でフルーツが多いカフジで集団の大きさと構成が異なることが分かりました。これを論文に出したのは2009年です。ここまで来て環境という外部要因による採食戦略、群れ内外の社会関係による内部要因が社会構造の変異をもたらしていることが分かってきたように感じました。
採食戦略と社会構造
次に興味を持ったのは、ゴリラとチンパンジーが一緒の場所に棲んでいながら全く異なる社会構造をもつことでした。調査の結果、両種とも主食のフルーツは同じでありながら、補助食物とその食べ方が違うことが分かりました。フルーツが不足するとゴリラは草を広範囲に移動して食べ、チンパンジーはあまり移動せずに昆虫や動物を食べます。そしてこの補助食物の採食戦略の違いによって進化史上進出した地域が異なり、その条件に合うように社会構造を変えたと言えるのではないかと思っています。食物の分配様式による人類の社会性の進化
食物の分配がゴリラやチンパンジーと同様に人類の社会性の根本にあると考えています。その場で食物を分配する類人猿と異なり、人類は食物を手で運び、安全な場所を確保して仲間と一緒に食べた。そして、肉食獣による捕食圧に対抗するために多産になり、なお且つ、200万年前ぐらいに脳を大きくするために体脂肪の厚い重たい赤ちゃんを産むようになった。その代わり身体の成長を遅らせて、子ども期という人間だけにある期間ができ、その間共同保育をしなくてはならなくなった。ここから家族と共同体という二重構造を持つ人間独自の社会性が始まりました。仲間が緊密に協力し合う大きな社会力を手にし、熱帯雨林から様々な大陸へと進出を始めることになったと考えられます。そして共食や共同保育によって育てられた高い共感力で、人間は一生涯自分が出てきた共同体にアイデンティティを持ち続け、そして集団というものを強く意識することになりました。そこに7万年ぐらい前に言葉が登場して認知革命が起こり、共感と対話という能力が結びついて想像力と創造力が拡大することになります。
人類学の行方
人類は、移動、集合、対話という3つの自由を使って、変容可能な社会を作り、人間独自の文化が生まれたと考えています。しかしなぜ人類は豊かな熱帯雨林を出たのか、なぜ宗教や科学という思考様式が生まれたのか、といった問題については未解明です。また、社会の変容に共感力を駆使したため、上述のように集団帰属意識が高まり、それが言語の発達、定住生活によって、集団間の敵対性が高まってそれが集団間の暴力を生み出すようになったという負の特徴も生まれました今日地球はいくつかの指標で限界値に達し、情報革命による意識と知能の分離が起こり、遺伝子編集、生物工学による人間の改造の可能性が進む中、新たな人間の社会性を再構築しなくてはなりません。その時に故きを温ね、人間に近い隣人の行動様式や社会を探る霊長類学、人類学がお役に立てるだろうと思っています。